日本はなぜ、30年も経済が停滞し続けてきたのか?
なぜ国民は豊かにならず、給料も上がらず、増税ばかりされるのか?
その答えの一つは、「貨幣に対する間違った理解=貨幣観のズレ」にあります。
💰 そもそも「お金」って何?
多くの人が、政府のお金を「自分の財布」と同じように捉えています。
- 「税金を集めて、それで支出する」
- 「借金が増えると破綻する」
- 「将来世代にツケが回る」
こういった考え方は、実はすべてズレています。
✅ 本当はこうです:
- 政府は通貨の「発行者」
- 民間(家計・企業)は通貨の「利用者」
- 政府は「支出してから税で回収する」
- 税金は財源ではなく、「インフレ抑制と再分配」のための調整弁
つまり、政府はお金を「作る」ことができます。
重要なのは、そのお金をどこに・どう配分するかという判断だけなのです。
🌀 デフレは“自然災害”ではない
インフレは、戦争・資源高・国際情勢などの外的要因で起こることがあります。
でもデフレは、完全に人為的な政策のミスによって起こります。
📉 デフレとは?
デフレーション(deflation)=物価が継続的に下がる現象です。
一見「物価が下がってラッキー!」に見えるかもしれませんが、実際には…
- 企業の売上が減る
- 給料が下がる
- 設備投資が減る
- 消費が冷え込む
という、経済全体の縮小スパイラルに陥ります。
教科書でも有名な言葉:「デフレスパイラル」
🚫 デフレ時にやってはいけない政策(教科書レベル)
| NG政策 | なぜダメか |
|---|---|
| 消費税増税 | 消費が冷え込み、物が売れなくなる |
| 財政支出の削減 | 政府が金を使わないと、需要が生まれない |
| 社会保障のカット | 将来不安が増し、貯蓄に回る |
| 賃金抑制 | 可処分所得が減り、経済が回らない |
中高の教科書にも書いてある通り、「デフレ期には需要を増やす政策(財政出動・減税)が必要」です。
デフレなのに、日本政府は真逆をやってきた
- 1997年・2014年・2019年:消費税増税
- 公共投資の削減、緊縮財政
- プライマリーバランス黒字化目標で歳出制限
- 社会保障費の抑制
- 非正規雇用の拡大で賃金低迷
まるで「国民を貧しくしたい勢力がいるのか?」と思ってしまうほどの政策ミスの連発でした。
🎯 背景にあるのは「間違った貨幣観」
貨幣(マネー)は「有限の資源」ではありません。
政府が発行・供給できる道具です。
でも、「借金=悪」「政府も節約すべき」という家計簿感覚の思い込みが、日本の政策判断を歪めてきました。
その結果が「失われた30年」なのです。
🧭 これから必要なのは「正しい貨幣観」
- 政府は通貨の発行者
- 支出の後に税で回収する仕組み
- 税はインフレ抑制・再分配のためのもの
- デフレ時には積極財政と減税こそが正解
- 国民の未来に投資する政治が必要
🔚 最後に
「国の借金が〜」という言葉にビクつき、政治が財布のヒモを締め続けた。
その結果が、30年にわたる停滞と、次世代の希望の喪失。
正しい貨幣観を持つこと。
それが、個人の行動だけでは超えられない「構造の壁」を壊す第一歩になります。
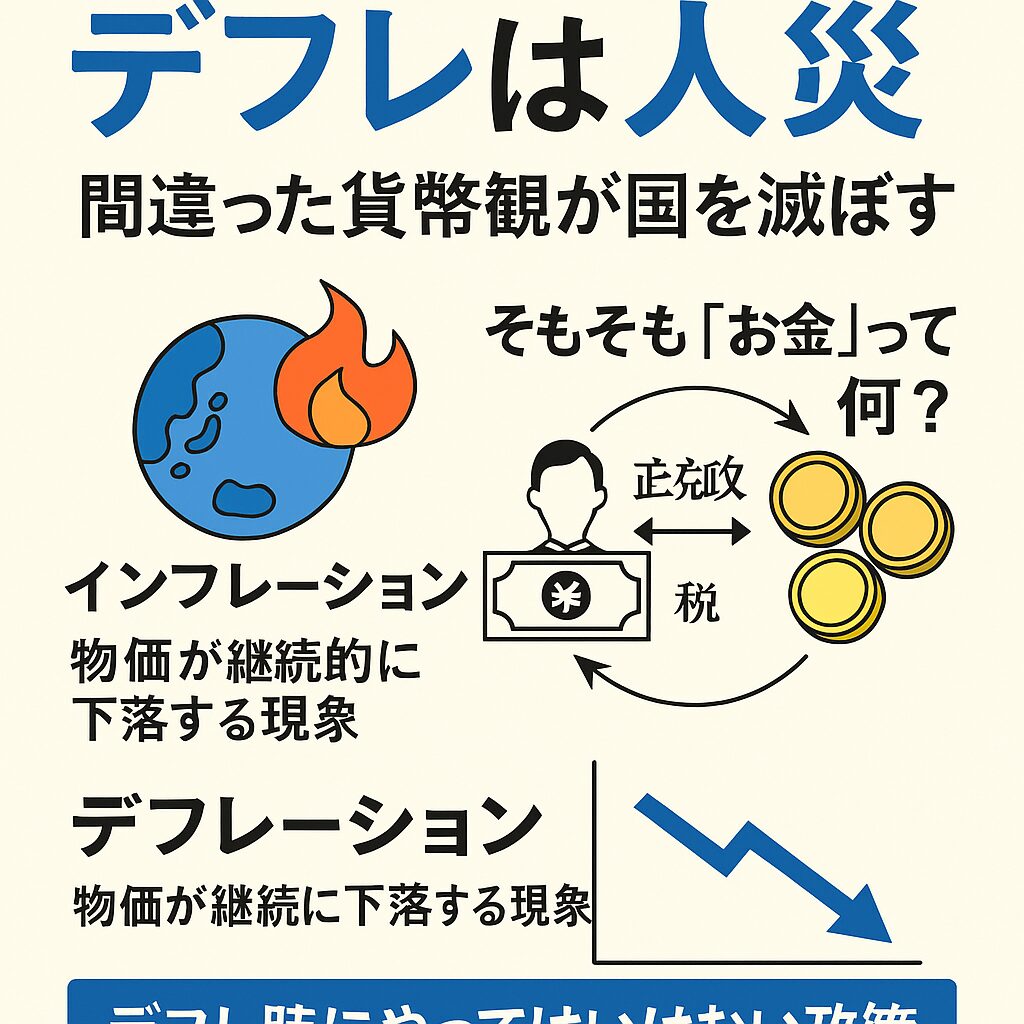

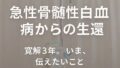
コメント